身体拘束最小化のための指針
1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方
沖縄協同病院の病院理念のもと「患者の人権」は公平に尊重される権利を保障しています。身体拘束は、患者の自由を制限することであり、療養生活に重大な影響を与えます。患者の人権を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束最小化に向け取り組みます。そのため、緊急・やむを得ない場合を除き、身体拘束は原則行いません。
2.身体拘束の定義
身体拘束とは、抑制帯、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限のことをいいます。
3.身体拘束に該当する行為
- 体幹抑制
- 四肢抑制・部分抑制(上肢/下肢)
- ミトン
- 車いす抑制帯(安全ベルト)
4.鎮静を目的とした薬剤の適正化
不眠時・不穏時の薬剤使用に関して適正化に向けた調整をすすめます。
5.身体拘束に該当しない行為
当院では、肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体拘束の対象とはなりません。
以下、具体的な行為
- 整形外科治療で用いるシーネ固定等
- 点滴時のシーネ固定・動脈ライン抜去時のシーネ固定等
- 転落防止のためのベッドの壁付け・4点柵使用・小児科で使用しているサークルベッド
- 自力座位が保持できない場合の車いすベルトの使用
- 身体拘束等をせずに患者を転倒や離院等のリスクから守る事故防止対策として使用する離床センサー等
6.身体拘束最小化のための体制
以下の取り組みを継続的に実施し、身体拘束最小化のための体制を維持・強化します。
1)身体拘束最小化委員会の設置・開催
身体拘束最小化委員会(以下委員会)を設置し、当院での身体拘束最小化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。また、過去・現在に緊急、または、やむを得ず身体拘束を行った場合の実施状況が適正であるか検討します。委員会は年4回程度開催します。
2)委員会の構成員とその役割
委員長:医師1名体制
役割【委員会の責任者及び諸課題の総括責任者】
委員:医師・看護師・薬剤師・理学療法士または作業療法士・公認心理師
役割【身体拘束最小化における適切な実施状況の把握・改善。身体拘束最小化に関わる職員教育】
3)委員会の検討項目
- 指針の見直し・改訂
- 身体拘束の実施状況の把握(数・方法など)
- 職員教育、院内・院外勉強会への参加促進
- 職員を対象とした身体拘束に関する情報を発信し共有
- 研修の実施日、方法、内容、参加者リストを記載した記録を作成
7.緊急にてやむを得ず身体拘束を行う場合の対応
身体拘束等は行わないことが原則であるが、患者または他の患者の生命又は身体を保護するための措置として・以下の【3要件】の全てを満たす状態にある場合には、患者、ご家族への説明同意を得たうえで身体拘束を行うことがあります。その場合でも患者の態様や看護ケアの見直し等により、早期の身体拘束解除に向けて取り組みます。
3要件の確認
- 切迫性:患者本人又は他の患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著 しく高いこと
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的であること
緊急、やむを得ず身体拘束を行う場合は以下の手順に沿って実施します。
複数人(2名以上・多職種参加が望ましい)で患者の状況・背景・3要件に該当するか検討し、医師の指示のもと患者・家族等の説明と書面で同意を得て行うことを原則とします。
8.身体拘束等に関する状況の把握と周知の方法
委員で実施状況を確認・評価した結果をイントラネットにて広報します。
9.本指針の閲覧
本指針はイントラネットにて全職員が閲覧可能とするほか、入院患者、家族、地域住民が閲覧できるようにホームページへ掲載します。
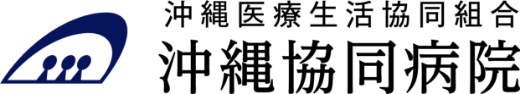
 HOME
HOME