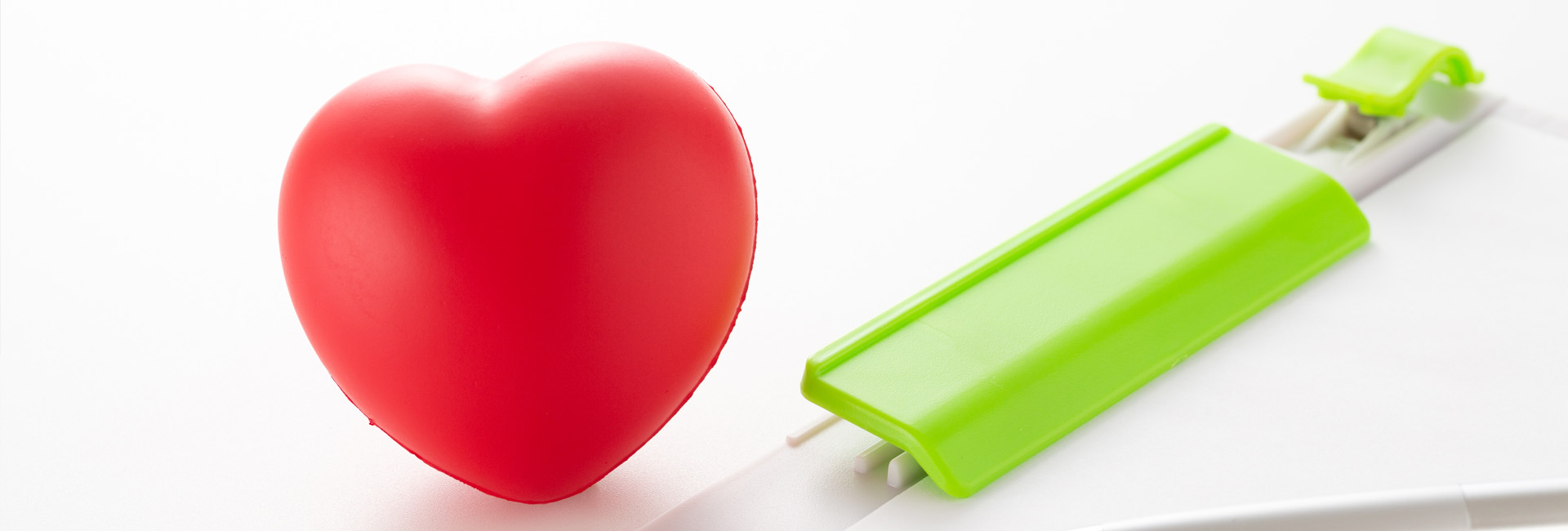 ">
">
CARDIOVASCULAR SURGERY
心臓血管外科
沖縄協同病院心臓血管外科は1983年に開設され、長崎大学心臓血管外科との関連施設として現在まで多くの手術を行ってきました。2013年以降は長崎大学との連携を強化したため症例数が増加し、ここ数年では年間60−70例程度の心臓手術と、100例程度の末梢血管手術を行っています。
冠動脈疾患に対しては心臓を止めずに行う心拍動下冠動脈バイパス手術を、弁膜症に対しては右開胸小切開手術で自己弁を温存する弁形成術を積極的に取り入れています。大動脈瘤に対しては血管内治療としてステントグラフト手術を行っています。また2017年から下肢静脈瘤に対してレーザー血管内焼灼術を開始しました。いずれの手術も低侵襲を目的とし、患者さんが早期に社会復帰ができるよう、日々工夫を行っています。
冠動脈疾患に対しては心臓を止めずに行う心拍動下冠動脈バイパス手術を、弁膜症に対しては右開胸小切開手術で自己弁を温存する弁形成術を積極的に取り入れています。大動脈瘤に対しては血管内治療としてステントグラフト手術を行っています。また2017年から下肢静脈瘤に対してレーザー血管内焼灼術を開始しました。いずれの手術も低侵襲を目的とし、患者さんが早期に社会復帰ができるよう、日々工夫を行っています。
 ">
">
診療体制表
| 診療開始-受付終了 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 予約 |
手術(開心術) |
橋本亘 |
手術(開心術) |
- |
橋本亘 東理人 |
|
| 午後 14:00~16:00 予約 |
- |
- |
- |
東理人 |
- |
|
代診・休診のお知らせ
お問い合わせ
医師紹介
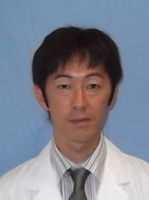
副院長
橋本 亘
Wataru Hashimoto
- 出身校(卒年)久留米大学 (1998年卒)
- 専門分野成人心臓外科 / 大血管外科
- 資格医学博士
三学会構成心臓血管外科専門医認定機構心臓血管外科修練指導者
三学会構成心臓血管外科専門医認定機構心臓血管外科専門医
日本循環器学会認定循環器専門医
日本脈管学会認定脈管専門医/指導医
日本血管外科学会認定血管内治療医
下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準による実施医/指導医
胸部ステントグラフト実施医
腹部ステントグラフト実施医/指導医
日本外科学会外科専門医/指導医
浅大腿動脈ステントグラフト実施医
低侵襲心臓手術認定医 - 所属学会日本外科学会
日本心臓血管外科学会
日本胸部外科学会
日本循環器学会
日本血管外科学会
日本心臓リハビリテーション学会
日本脈管学会
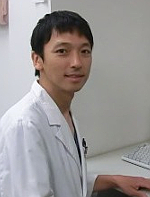
心臓血管外科医長(外来)
東 理人
Rihito Higashi
- 出身校(卒年)関西医科大学(2007年卒)
- 専門分野成人心臓外科 / 大血管外科 / 末梢血管外科
- 資格三学会構成心臓血管外科専門医認定機構心臓血管外科専門医/修練指導者
日本循環器学会認定循環器専門医
下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準による実施医/指導医
胸部ステントグラフト実施医/指導医
腹部ステントグラフト実施医/指導医
日本血管外科学会認定血管内治療医
日本外科学会外科専門医
浅大腿動脈ステントグラフト実施医
日本脈管学会脈管専門医/指導医 - 所属学会日本外科学会
日本心臓血管外科学会
日本胸部外科学会
日本血管外科学会
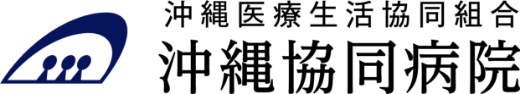
 HOME
HOME